2013年04月26日
第7回 酔読ノススメ
当コラム第3回「17歳の酒縁」(≫こちら)で紹介した、『喜久醉純米大吟醸松下米』の原料米生産農家・松下明弘さんが、【ロジカルな田んぼ】(日経プレミアシリーズ)という新書本を上梓しました。
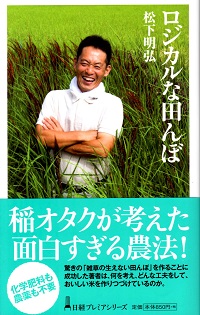
独学で辿り着いた〈農薬や化学肥料を使わないのに雑草が生えなくなった田んぼづくり〉のプロセスを通し、農作業のすべてに理由があることを、学者の論説ではなく自称稲オタクとして実証したもの。〈有機農業〉の本意や、「17歳の酒縁」でも触れた喜久醉の蔵元との出会い、巨大胚芽米カミアカリを育種した経緯など等、農業者自身がここまでクレバーに語り切るなんて、ニッポン農業は新しい次元に進化したんじゃないかと感じさせる筆力です。たまたま発刊直後の4月12日、所用で上京して新宿紀伊国屋書店の新刊本コーナーをのぞいたら、名だたるベストセラーと並んでセンターポジションに堂々と並んでいて、胸が熱くなりました。
2000年10月、藤枝市出身の写真家多々良栄里さんが、松下さんを密着撮影した連作「松下君の山田錦」(土門拳文化奨励賞受賞)を新宿コニカプラザで展示披露した際、松下さんと2人で観に行き、本屋に寄りたいと言う彼につきあって、新宿紀伊国屋書店で長々時間をつぶしたことがありました。本などに頼らず、トコトン現場・実践主義を貫く人だと思っていた彼が専門書を漁っている姿に、少々意外な感じがしましたが、こうして、この書店の新刊センターポジションに著作を並べてしまう日が来るとは・・・。
今回は【ロジカルな田んぼ】が加わったMY書棚から、読むだけで心地よく酔いそうな、お気に入り本をご紹介します。

桜木廂夫さんの【名酒発掘の旅】(平凡社/1987年刊)は、私が地酒の取材を始めて最初に購入したガイド本でした。「傳魚坊」「笹舟」「松島」等と並び、地酒を育てた料飲店として名高い神田「一ノ茶屋」店主が綴った酒蔵訪問記で、静岡県では『春の甍』という酒が紹介されています。ピンと来ない人も多いでしょう。これ、藤枝の『志太泉』が当時、首都圏向けに発売していた純米酒ブランドです。久しぶりに読み返して気がついたんですが、桜木さんは「この酒蔵に今期、一升瓶で五千本の純米酒を注文している」と書いています。個人店一店の注文数か!?と目を疑いましたが、当時はこういう個店が、地方の隠れた名酒を買い支えていたんだなあと感慨深くなりました。
それはさておき、桜木さんは、当時の志太泉の杜氏が、桜木さんの常識を超える洗米作業と麹造りをしていたこと、若い酒造技術者が熱心に指導している光景を紹介しています。ピンと来る人もいるでしょう。杜氏は多田信男さん。今は磯自慢の杜氏さんです。若い技術者というのは静岡県工業技術センター(当時)で静岡酵母を開発した河村傳兵衛さんで、多田さんと同い年の43歳。お二人ともバリバリの働き盛りでした。
桜木さんが、静岡酵母や酒造りの技術全般について質問しても、河村さんからは判で押したように「酵母だけでは名酒はできない」「酵母より麹のほうが大切」「しっかりした麹を造らないといけません」と返ってきます。とりわけ印象的だったのは、「(河村氏は)麹造りは建築で言うならば、土台であり骨組みだと言った。酵母の役割は内装であり、外装であり、いわばインテリアの部分に属する、とも言った」という一節です。酒の勉強を始めたばかりの若輩者にとって、麹と酵母¬=2大微生物の働きや役割を正しく理解することは最初の大きな関門。これをすんなり通過させてくれたバイパスのような一節でした。
この本は、志太泉さんや河村さんに薦められたわけではなく、書店でたまたま見つけ、静岡の蔵が載っている数少ない本だったのでとりあえず買ってみたんですが、その後に出会った酒の関係者の中で「麹造りの重要性をしっかり語れる人」とそうではない人では、物事の本質を語っているのか、そもそも本質を理解しているかが、なんとなく見えてきました。
酒に限りません。料理人ならダシ、農家なら土づくり、企業経営者なら基本となるシステムづくりや人員配置・・・。インタビューでグッと心を掴まされるのは、こういう話を、時間を割いて語る人です。基礎の土台をしっかり作ることに手を抜かず、真摯に取り組む人、ですね。最初に読んだ酒の本で、土台というキーワードで酒造りの核心を突いた一節に出会えたというのは、私の取材活動にとって実に大きかった。
この本を買った直後に、河村さんから「よかったら読んでみてください」と薦められたのがこの本でした(笑)。そのときの、照れくさそうな表情を、昨日のことのように覚えています。

藤田千恵子さんの【杜氏という仕事】(新潮新書/2004年刊)は、自分もいつか、酒の分野でこういうものが書けるようになりたいと具体的にイメージできた本です。著者の藤田さんも、こういうライターになりたいと思わせる憧れの女性。何度かお会いし、しずおか地酒研究会で講演に来ていただいたこともあります。とても面白い講演&蔵元セッションだったので、よかったらこちらをご覧ください。
◆藤田さんの講演
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2008/04/post_1c05.html
◆藤田さんvs國香・杉錦・志太泉・喜久醉トークセッション
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2008/04/vs_4edd.html
本書は、滋賀県の銘酒『喜楽長』を醸す能登杜氏・天保正一さんのロングインタビューを柱に、杜氏という日本の伝統的な技能者の職業観や人生観、日本酒の造り手が置かれた環境や酒造業の未来について、じっくり読ませてくれます。
この本にもお気に入りの一節があります。
「杜氏はね、眠れん夜があるものですよ。(中略)酒造りの責任者には、孤独なところもあるのですよ。でも、その責任で苦労する部分と、自分の技術で対応していくおもしろみと、両方を味わうようにならないと、杜氏はだめですね。結局、酒造りというのは、何年やっても、これでいい、ということがない。去年どおりでもだめなんです。(中略)自分の理想通りには、なかなか進まない。その面だけ孤独なんですよ」。
名人と謳われる職人が〈孤独〉という言葉を吐く・・・このことの重さが、モノづくりの取材をしていく上でいつも脳裏に甦ってきます。
文中、天保さんに憧れ、蔵元・喜多酒造に直談判して蔵人になった西原光志さんという若者が登場します。ピンと来る人もいると思いますが、今、西原さんは、『志太泉』の杜氏を務めています。なんとも不思議な酒縁ですよね。

吉田健一さんの【まろやかな日本】(新潮社/1978年刊)は、発刊年は前2冊よりも古いのですが、出会ったのは2年前。しずおか地酒研究会で企画した『酒と匠の文化祭』というイベントの中で、フリーアナウンサー國本良博さんに酒の本の朗読をお願いした中の一冊です。朗読会の様子はこちらをご覧ください。
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_ea42.html
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_2948.html
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_3123.html
國本さんにはこのとき、井伏鱒二や若山牧水の歌、篠田次郎さんの酒の歳時記、不肖私の県内酒蔵レポート等を読んでもらったのですが、せっかくプロのアナウンサーに頼むなら、読むのはしんどいけど心地よい朗読なら多少は耳に入るかも・・・という、ちょっと高尚な酒文化論も入れようと思い、あれこれ探して発掘しました。
著者の吉田さんは、昭和の宰相吉田茂のご長男。英国タイムズ紙に「完全無比な英語を使いこなす日本の英文学者」と紹介された人で、本書は1974年、イギリスで「Japan is a circle」というタイトルで出版され、吉田さんが亡くなった1年後に日本で翻訳・出版された日本文化論です。全26章のうち、日本酒について4章が費やされており、何度も読み込んでワードのテキストに入力し、國本さんと相談して音読に適さない部分をカットし、朗読用台本に仕上げました。一部を再掲します。
「日本酒というものの絶妙さは、飲んでみなければとうてい信じられるものではない。多くの要素が、といっても量ではなく、質の点で入り組んだ日本の食事には、1回の献立のなかに胡桃から鶉や熊の足といったものまで含まれている場合もありうるが、日本酒はその全部と合う。
ある人が一度、日本酒でビフテキを食べたことがあって、これも申し分なく合ったらしい。しかしむろん、何を一緒に食べようと、そんなことは酒自体に比べればほとんど問題にならない。この点で日本酒は葡萄酒に優るのであって、全然何も食べないか、せいぜい塩をちょっと舐める程度でもすむ。つまり、いい酒ができるのに役立っている複雑な成分がそこにあれば、あとはただ盃を口へ運ぶこと以外、現実には何一つしないで充分だということである。
日本酒はほとんど、どんな食べ物とも合うだけでなく、それ自体、ほとんど、どんなものにも成り得る。西洋ではどの国だろうと人は大理石の大広間でシャンパンを飲み、安酒場でジンを飲む。日本では、同じ日本酒を、金箔で飾り立てた豪華な座敷で飲むこともあれば、馬方が出入りする道端の小さな屋台で、縁に少しばかり塩をのせた四角い杉材の容器に入れて飲むこともある。
日本酒が、そうした屋台でのほうがかえっていい状態に保たれていることさえあるかもしれないのは、少なくとも上流階級よりも馬方のほうが自分たちの飲むものに気を配るからであって、少なくともそういう階級が存在していた頃はそうだった。」(第15章「日本酒の定義」より抜粋)。
英語の翻訳文で朗読しづらい表現が多かったにもかかわらず、國本さんの艶やかで抑揚のある声によって、吉田さん自身が、新橋あたりのガード下の飲み屋を恋しく思い浮かべ、ロンドンのセレブたちに滔々と語って聞かせている・・・そんな情景が浮かんできました。呑みながら聴くっていうのが、またいいんですよねえ。
國本さんは、しずおか地酒研究会設立のきっかけとなった、1995年の静岡市南部図書館地酒講座のプログラムに、地酒エッセイの寄稿をお願いして以来のおつきあい。エッセイを頼んだきっかけは、國本さんがラジオ番組で河村傳兵衛さんにインタビューしていたのを偶然聴いて、とても面白くて、静岡新聞社の知り合いに仲介を頼んだのです。その後、それまで日本酒を敬遠していた國本さんを、無事、こちら側?に寝返させることが出来ました(笑)。
日本酒の朗読ライブは、國本さんと私のライフワークにできればいいなあと思っています。

2010年12月、大旅籠柏屋(岡部)で開催した「酒と匠の文化祭」での國本良博さんの酒の朗読会
新宿紀伊国屋で【ロジカルな田んぼ】を購入した日の夜、広尾の日赤通りにある定食店『一汁三菜』で、喜久醉純米吟醸松下米と、カミアカリ(松下さんが育種した巨大胚芽米)の玄米ご飯を味わいました。松下さんの米をこよなく愛する店主の朝川佳子さんと、本の話や喜久醉の県知事賞受賞の話題でひとしきり盛り上がりました。
【ロジカルな田んぼ】でお気に入りの一節は、
「自然の摂理にさからわないこと。さまざまな生きものの有機的つながりをこわさないよう、人間も自然の摂理のなかで動くこと」「田んぼの持ち主は松下になっているけれど、決して私一人のものじゃない。多くの生きものの生活の場になっている。そこで産まれ、そこで育ち、そこで死に、その死骸がまた田んぼの栄養になっていく。こうした循環から、少しだけおすそ分けをもらうのが有機農業だと思うのです」(92~93ページ)。
ここを読むと、ふと、禅の教えが浮かんでくるのです。無我の境地とは、田んぼの中の微生物のように、有機的つながりに身をゆだねるということだろう、と、腑に落ちる。
私は年に数回、京都の禅寺に坐禅をしに行きます。無我になろうと意識するうちは、なかなかなれないんですが、和尚から薦められた盛永宗興さん(元・妙心寺塔頭大珠院住職)の【お前は誰か】(禅文化研究所/2005年刊)に、こんな一節があります。

「DNAは生物の最も基本的な内在情報であって、細胞が一箇しかない単細胞生物から、人間のように数兆規模の細胞を持つ多細胞生物にいたるまで、例外なく共通に持っている物質です。(中略)すべてに共通して含まれるということ、この意味で、普遍的な〈いのち〉と、多様性を持った種種雑多な存在が、実は一つであるといえる。岡田博士は「一即多多即一」という仏教的な概念を、生物学の立場からお話された」。
岡田博士というのは、盛永さんが学長を務めた花園大学の文化祭に講師で招いた発生生物学の世界的権威・岡田節人博士のこと。評論家立花隆さんと脳死について対談したNHKの番組を盛永さんがご覧になり、講師に招かれたようです。
松下さんの田んぼは、宇宙にも喩えられる般若心経の世界を具現化したものではないか・・・。彼の山田錦で醸した酒と、玄米カミアカリを咀嚼していると、そんな妄想にとらわれてしまいます。
酒に関係のない話に飛んでいきそうなので、このへんで杯を眠らせておきますが、古い本でもネットで取り寄せられる便利な時代になりましたので、興味があったら読んでみてください。ちなみに【ロジカルな田んぼ】、東京の有名書店ではセンターポジションなのに、静岡の書店ではとんと見かけません。かつての静岡地酒と同じ扱いですね(苦笑)。・・・静岡の書店の奮起に期待します!
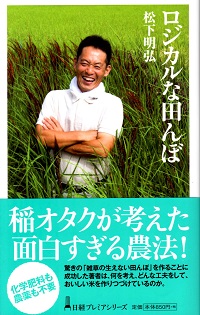
独学で辿り着いた〈農薬や化学肥料を使わないのに雑草が生えなくなった田んぼづくり〉のプロセスを通し、農作業のすべてに理由があることを、学者の論説ではなく自称稲オタクとして実証したもの。〈有機農業〉の本意や、「17歳の酒縁」でも触れた喜久醉の蔵元との出会い、巨大胚芽米カミアカリを育種した経緯など等、農業者自身がここまでクレバーに語り切るなんて、ニッポン農業は新しい次元に進化したんじゃないかと感じさせる筆力です。たまたま発刊直後の4月12日、所用で上京して新宿紀伊国屋書店の新刊本コーナーをのぞいたら、名だたるベストセラーと並んでセンターポジションに堂々と並んでいて、胸が熱くなりました。
2000年10月、藤枝市出身の写真家多々良栄里さんが、松下さんを密着撮影した連作「松下君の山田錦」(土門拳文化奨励賞受賞)を新宿コニカプラザで展示披露した際、松下さんと2人で観に行き、本屋に寄りたいと言う彼につきあって、新宿紀伊国屋書店で長々時間をつぶしたことがありました。本などに頼らず、トコトン現場・実践主義を貫く人だと思っていた彼が専門書を漁っている姿に、少々意外な感じがしましたが、こうして、この書店の新刊センターポジションに著作を並べてしまう日が来るとは・・・。
今回は【ロジカルな田んぼ】が加わったMY書棚から、読むだけで心地よく酔いそうな、お気に入り本をご紹介します。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

桜木廂夫さんの【名酒発掘の旅】(平凡社/1987年刊)は、私が地酒の取材を始めて最初に購入したガイド本でした。「傳魚坊」「笹舟」「松島」等と並び、地酒を育てた料飲店として名高い神田「一ノ茶屋」店主が綴った酒蔵訪問記で、静岡県では『春の甍』という酒が紹介されています。ピンと来ない人も多いでしょう。これ、藤枝の『志太泉』が当時、首都圏向けに発売していた純米酒ブランドです。久しぶりに読み返して気がついたんですが、桜木さんは「この酒蔵に今期、一升瓶で五千本の純米酒を注文している」と書いています。個人店一店の注文数か!?と目を疑いましたが、当時はこういう個店が、地方の隠れた名酒を買い支えていたんだなあと感慨深くなりました。
それはさておき、桜木さんは、当時の志太泉の杜氏が、桜木さんの常識を超える洗米作業と麹造りをしていたこと、若い酒造技術者が熱心に指導している光景を紹介しています。ピンと来る人もいるでしょう。杜氏は多田信男さん。今は磯自慢の杜氏さんです。若い技術者というのは静岡県工業技術センター(当時)で静岡酵母を開発した河村傳兵衛さんで、多田さんと同い年の43歳。お二人ともバリバリの働き盛りでした。
桜木さんが、静岡酵母や酒造りの技術全般について質問しても、河村さんからは判で押したように「酵母だけでは名酒はできない」「酵母より麹のほうが大切」「しっかりした麹を造らないといけません」と返ってきます。とりわけ印象的だったのは、「(河村氏は)麹造りは建築で言うならば、土台であり骨組みだと言った。酵母の役割は内装であり、外装であり、いわばインテリアの部分に属する、とも言った」という一節です。酒の勉強を始めたばかりの若輩者にとって、麹と酵母¬=2大微生物の働きや役割を正しく理解することは最初の大きな関門。これをすんなり通過させてくれたバイパスのような一節でした。
この本は、志太泉さんや河村さんに薦められたわけではなく、書店でたまたま見つけ、静岡の蔵が載っている数少ない本だったのでとりあえず買ってみたんですが、その後に出会った酒の関係者の中で「麹造りの重要性をしっかり語れる人」とそうではない人では、物事の本質を語っているのか、そもそも本質を理解しているかが、なんとなく見えてきました。
酒に限りません。料理人ならダシ、農家なら土づくり、企業経営者なら基本となるシステムづくりや人員配置・・・。インタビューでグッと心を掴まされるのは、こういう話を、時間を割いて語る人です。基礎の土台をしっかり作ることに手を抜かず、真摯に取り組む人、ですね。最初に読んだ酒の本で、土台というキーワードで酒造りの核心を突いた一節に出会えたというのは、私の取材活動にとって実に大きかった。
この本を買った直後に、河村さんから「よかったら読んでみてください」と薦められたのがこの本でした(笑)。そのときの、照れくさそうな表情を、昨日のことのように覚えています。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

藤田千恵子さんの【杜氏という仕事】(新潮新書/2004年刊)は、自分もいつか、酒の分野でこういうものが書けるようになりたいと具体的にイメージできた本です。著者の藤田さんも、こういうライターになりたいと思わせる憧れの女性。何度かお会いし、しずおか地酒研究会で講演に来ていただいたこともあります。とても面白い講演&蔵元セッションだったので、よかったらこちらをご覧ください。
◆藤田さんの講演
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2008/04/post_1c05.html
◆藤田さんvs國香・杉錦・志太泉・喜久醉トークセッション
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2008/04/vs_4edd.html
本書は、滋賀県の銘酒『喜楽長』を醸す能登杜氏・天保正一さんのロングインタビューを柱に、杜氏という日本の伝統的な技能者の職業観や人生観、日本酒の造り手が置かれた環境や酒造業の未来について、じっくり読ませてくれます。
この本にもお気に入りの一節があります。
「杜氏はね、眠れん夜があるものですよ。(中略)酒造りの責任者には、孤独なところもあるのですよ。でも、その責任で苦労する部分と、自分の技術で対応していくおもしろみと、両方を味わうようにならないと、杜氏はだめですね。結局、酒造りというのは、何年やっても、これでいい、ということがない。去年どおりでもだめなんです。(中略)自分の理想通りには、なかなか進まない。その面だけ孤独なんですよ」。
名人と謳われる職人が〈孤独〉という言葉を吐く・・・このことの重さが、モノづくりの取材をしていく上でいつも脳裏に甦ってきます。
文中、天保さんに憧れ、蔵元・喜多酒造に直談判して蔵人になった西原光志さんという若者が登場します。ピンと来る人もいると思いますが、今、西原さんは、『志太泉』の杜氏を務めています。なんとも不思議な酒縁ですよね。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

吉田健一さんの【まろやかな日本】(新潮社/1978年刊)は、発刊年は前2冊よりも古いのですが、出会ったのは2年前。しずおか地酒研究会で企画した『酒と匠の文化祭』というイベントの中で、フリーアナウンサー國本良博さんに酒の本の朗読をお願いした中の一冊です。朗読会の様子はこちらをご覧ください。
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_ea42.html
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_2948.html
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_3123.html
國本さんにはこのとき、井伏鱒二や若山牧水の歌、篠田次郎さんの酒の歳時記、不肖私の県内酒蔵レポート等を読んでもらったのですが、せっかくプロのアナウンサーに頼むなら、読むのはしんどいけど心地よい朗読なら多少は耳に入るかも・・・という、ちょっと高尚な酒文化論も入れようと思い、あれこれ探して発掘しました。
著者の吉田さんは、昭和の宰相吉田茂のご長男。英国タイムズ紙に「完全無比な英語を使いこなす日本の英文学者」と紹介された人で、本書は1974年、イギリスで「Japan is a circle」というタイトルで出版され、吉田さんが亡くなった1年後に日本で翻訳・出版された日本文化論です。全26章のうち、日本酒について4章が費やされており、何度も読み込んでワードのテキストに入力し、國本さんと相談して音読に適さない部分をカットし、朗読用台本に仕上げました。一部を再掲します。
「日本酒というものの絶妙さは、飲んでみなければとうてい信じられるものではない。多くの要素が、といっても量ではなく、質の点で入り組んだ日本の食事には、1回の献立のなかに胡桃から鶉や熊の足といったものまで含まれている場合もありうるが、日本酒はその全部と合う。
ある人が一度、日本酒でビフテキを食べたことがあって、これも申し分なく合ったらしい。しかしむろん、何を一緒に食べようと、そんなことは酒自体に比べればほとんど問題にならない。この点で日本酒は葡萄酒に優るのであって、全然何も食べないか、せいぜい塩をちょっと舐める程度でもすむ。つまり、いい酒ができるのに役立っている複雑な成分がそこにあれば、あとはただ盃を口へ運ぶこと以外、現実には何一つしないで充分だということである。
日本酒はほとんど、どんな食べ物とも合うだけでなく、それ自体、ほとんど、どんなものにも成り得る。西洋ではどの国だろうと人は大理石の大広間でシャンパンを飲み、安酒場でジンを飲む。日本では、同じ日本酒を、金箔で飾り立てた豪華な座敷で飲むこともあれば、馬方が出入りする道端の小さな屋台で、縁に少しばかり塩をのせた四角い杉材の容器に入れて飲むこともある。
日本酒が、そうした屋台でのほうがかえっていい状態に保たれていることさえあるかもしれないのは、少なくとも上流階級よりも馬方のほうが自分たちの飲むものに気を配るからであって、少なくともそういう階級が存在していた頃はそうだった。」(第15章「日本酒の定義」より抜粋)。
英語の翻訳文で朗読しづらい表現が多かったにもかかわらず、國本さんの艶やかで抑揚のある声によって、吉田さん自身が、新橋あたりのガード下の飲み屋を恋しく思い浮かべ、ロンドンのセレブたちに滔々と語って聞かせている・・・そんな情景が浮かんできました。呑みながら聴くっていうのが、またいいんですよねえ。
國本さんは、しずおか地酒研究会設立のきっかけとなった、1995年の静岡市南部図書館地酒講座のプログラムに、地酒エッセイの寄稿をお願いして以来のおつきあい。エッセイを頼んだきっかけは、國本さんがラジオ番組で河村傳兵衛さんにインタビューしていたのを偶然聴いて、とても面白くて、静岡新聞社の知り合いに仲介を頼んだのです。その後、それまで日本酒を敬遠していた國本さんを、無事、こちら側?に寝返させることが出来ました(笑)。
日本酒の朗読ライブは、國本さんと私のライフワークにできればいいなあと思っています。
2010年12月、大旅籠柏屋(岡部)で開催した「酒と匠の文化祭」での國本良博さんの酒の朗読会
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
新宿紀伊国屋で【ロジカルな田んぼ】を購入した日の夜、広尾の日赤通りにある定食店『一汁三菜』で、喜久醉純米吟醸松下米と、カミアカリ(松下さんが育種した巨大胚芽米)の玄米ご飯を味わいました。松下さんの米をこよなく愛する店主の朝川佳子さんと、本の話や喜久醉の県知事賞受賞の話題でひとしきり盛り上がりました。
【ロジカルな田んぼ】でお気に入りの一節は、
「自然の摂理にさからわないこと。さまざまな生きものの有機的つながりをこわさないよう、人間も自然の摂理のなかで動くこと」「田んぼの持ち主は松下になっているけれど、決して私一人のものじゃない。多くの生きものの生活の場になっている。そこで産まれ、そこで育ち、そこで死に、その死骸がまた田んぼの栄養になっていく。こうした循環から、少しだけおすそ分けをもらうのが有機農業だと思うのです」(92~93ページ)。
ここを読むと、ふと、禅の教えが浮かんでくるのです。無我の境地とは、田んぼの中の微生物のように、有機的つながりに身をゆだねるということだろう、と、腑に落ちる。
私は年に数回、京都の禅寺に坐禅をしに行きます。無我になろうと意識するうちは、なかなかなれないんですが、和尚から薦められた盛永宗興さん(元・妙心寺塔頭大珠院住職)の【お前は誰か】(禅文化研究所/2005年刊)に、こんな一節があります。

「DNAは生物の最も基本的な内在情報であって、細胞が一箇しかない単細胞生物から、人間のように数兆規模の細胞を持つ多細胞生物にいたるまで、例外なく共通に持っている物質です。(中略)すべてに共通して含まれるということ、この意味で、普遍的な〈いのち〉と、多様性を持った種種雑多な存在が、実は一つであるといえる。岡田博士は「一即多多即一」という仏教的な概念を、生物学の立場からお話された」。
岡田博士というのは、盛永さんが学長を務めた花園大学の文化祭に講師で招いた発生生物学の世界的権威・岡田節人博士のこと。評論家立花隆さんと脳死について対談したNHKの番組を盛永さんがご覧になり、講師に招かれたようです。
松下さんの田んぼは、宇宙にも喩えられる般若心経の世界を具現化したものではないか・・・。彼の山田錦で醸した酒と、玄米カミアカリを咀嚼していると、そんな妄想にとらわれてしまいます。
酒に関係のない話に飛んでいきそうなので、このへんで杯を眠らせておきますが、古い本でもネットで取り寄せられる便利な時代になりましたので、興味があったら読んでみてください。ちなみに【ロジカルな田んぼ】、東京の有名書店ではセンターポジションなのに、静岡の書店ではとんと見かけません。かつての静岡地酒と同じ扱いですね(苦笑)。・・・静岡の書店の奮起に期待します!
Posted by 日刊いーしず at 12:00
2013年04月12日
第6回 酒造業界のミスコン・新酒鑑評会
数年前のこと。酒造関係者の間で衝撃的な数字が話題になりました。国内で消費されるアルコール飲料のうち、日本酒のシェアは、わずか8%。静岡市の繁華街、両替町や常磐町あたりで飲み歩く人がひと晩で何人いるのか数えたことはありませんが、100人いたとしたら、8人しか日本酒を飲んでいないなんて・・・。
さらに、全国に流通されている日本酒のうち、静岡県の酒はたったの0.68%。地元なら高いだろうと思ったら県内で流通されている日本酒の中で静岡の酒は20%以下。地酒ファンが憤慨したくなる数字です・・・。確かに気候温暖な静岡県は、酒どころというイメージがないし、すっかり全国区のグルメスポットになった青葉おでん横丁でも、静岡割り(焼酎のお茶割り)は人気だけど、地酒をガンガン飲む客、売る店はありません。
それでも、静岡県内で生産される日本酒は、全国の酒通の間で「吟醸王国」とまで称されるほど人気があるって、信じられますか?
今回は静岡県が吟醸王国になったきっかけともいえる、新酒鑑評会=酒の品質コンテストのディープな世界にご案内しましょう。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
県内の酒蔵は30社ほど。多くは江戸時代に創業した老舗企業です。東海道の宿場町整備によって消費地が形成され、どの町にも必ず造り酒屋があったんですね。中には商才に長けた近江商人が隠密活動の拠点代わりに開業した、なんて蔵もあります。
明治以降は酒税を重要な国税にしようと、国が積極的に酒造業を奨励します。このころ設立されたのが国立の醸造試験所。酒税は国の税収の3割を占めるまでになっていましたが、当時は醸造技術が未熟だったため、品質劣化がしばしば問題になりました。宿場町の酒屋の軒先で量り売りする程度ならまだしも、大量に造って各地へ出荷するとなると品質を安定させなければなりません。税金をあてこんでいる国としても、ちゃんと造ってどんどん売ってもらわないと困るということで、国策で醸造試験所を造り、品質コンテスト=全国新酒鑑評会をスタートさせたのです。
この、全国新酒鑑評会。今年でなんと101回目です。休止したのは戦争中と、「独立行政法人酒類総合研究所」に移行する際に東京から東広島へ施設移転したときだけ。全国規模のコンペティションでこれだけ長く継続し、しかも内容的にも非常にレベルの高い技術コンテストというのは世界でも稀有な存在です。
市販酒の生産拡大のために酒造技術を向上させるという目的でスタートした鑑評会は、やがて蔵元や杜氏にとって、国から優良とのお墨付きをもらい、「金賞」を授与されることはこの上ない誉れとなり、しだいに技術競争の様相を呈してきます。鑑評会の出品用に原料の米を(米の外側は栄養があるが酒にすると雑味になるため)半分以下まで精米し、特別に吟味して醸す、という意味合いの「吟醸酒」は、ここから生まれました。
さまざまな清酒酵母が生まれ、実用化されるようになったのも、鑑評会の功績です。7号酵母、9号酵母といった名称で知られる酵母菌の多くは、鑑評会で好成績だった酒蔵を醸造試験所の技術者が調査し、酵母を収集し、保存・育種して普及させました。優良な酵母を選抜して安全な環境で培養し、全国の酒蔵へ頒布することは、日本酒全体の品質安定につながったのです。
現在、酵母は、日本醸造協会という業界団体が専門に培養しており、実用化した順に番号を付けています。現役の協会酵母で最も古いのは6号酵母で、大正時代に秋田の「新政」という蔵から採取されました。7号酵母は昭和21年に長野の「真澄」から。9号酵母は熊本の「香露」から出た香りの高い酵母で、吟醸酒向けに一世風靡しました。みなさんがイメージする吟醸酒のフルーティーな香りは、9号酵母が定着させたとも言われ、今でも鑑評会出品酒の多くは9号系統の酵母を使用しているようです。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
さて、静岡県。東海道の城下町を中心に、個人経営の小規模な蔵が多かったものの、交通の要所=安定した消費地という地理的条件に支えられ、そこそこ繁盛していました。しかしながら、太平洋戦争中は原料米不足の折から統廃合を余儀なくされ、生き残った蔵も、東海道線、国道1号線、東名高速道路という新たな交通の動脈が物流を加速させ、高度成長期には全国の銘醸地からさまざまな酒が流入し、地酒は存在感を失っていきます。日本酒の生産量のピークは昭和48年頃と言われていますが、静岡県の蔵元は昭和50年代前半頃まで灘や伏見の大手酒造会社の下請けで生計を立てるなど“日陰の時代”が続きました。
昭和50年代後半から下請けの量が減り始め、さらに経営が苦しくなった県内の蔵元は、それまで経営の柱には考えなかった「吟醸酒」で生き残りを図る英断をします。
この時に追い風となったのが静岡酵母。蔵元に技術指導をしていた静岡県工業技術センターの河村傅兵衛氏が、蔵元が自立するには他地域の亜流にならず、独自スタイルで勝負すべきと考え、吟醸酒造りの実績を持つ県内の蔵で発見した酵母菌をもとに、バイオテクノロジーを駆使して独自開発したものです。
昭和61年の全国新酒鑑評会には、県内から21銘柄が出品し、金賞10、銀賞7を獲得しました。入賞率は実に87%。2位石川県、3位福井県をおさえて全国一位という、県酒造史始まって以来の快挙を成し遂げました。
この年、全国新酒鑑評会に出品された酒は800銘柄ほどで、うち約100銘柄が金賞に選ばれたのですが、この中の10銘柄を静岡県が占めたのです。しかも9号酵母ではなく、地方研究機関が独自に開発した酵母による吟醸酒造り。酒どころとしては無名だった静岡県は、この年の鑑評会を機に、一躍、銘醸地に名乗りを上げたのでした。
他県の研究機関や蔵元は驚愕し、静岡酵母に着目します。「静岡で成功するなら当県だって・・・」と各県の酵母開発に勢いが付き、優良酵母の輩出県だった秋田や長野も新たに独自酵母を生み出します。長野県の「アルプス酵母」は、繊細でまるみのあるおだやかな香りの静岡酵母の酒とは異なる、香り華やかで濃厚な酒を醸し出し、その後の鑑評会で大量入賞しました。静岡酵母の酒が、薄化粧の素肌美人だとしたら、アルプス酵母は完璧な女優メイクを施した美女って感じでしょうか。
いずれにしても、静岡県が先鞭を付けた酵母開発と吟醸酒造りの技術革新は、それまで、国の指導による“鑑評会出品酒”の規格に、新たな地方化・個性化の波をもたらしたのでした。“美女の条件”は画一じゃなくなったってことですね!
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
全国新酒鑑評会は毎年5月に行われます。その前に、地域国税局単位の新酒鑑評会が4月(静岡県は東海4県を管轄する名古屋国税局に所属・現在は秋に開催)、県単位の鑑評会が3月に開かれます。
静岡県清酒鑑評会は、吟醸酒の部・純米酒の部と2つ部門があり、点数を付けて順位を決め、最上位の銘柄に県知事賞を授与します。順位を発表している県はあまり多くありません。

2012年全国新酒鑑評会(東広島市アリーナ)

2013年静岡県清酒鑑評会一般公開(グランディエールブケトーカイ)
各県でどういう酒に県知事賞を与えるかはさまざまです。私が以前、取材に行った宮城県清酒鑑評会は、県知事賞は宮城県の米を使った酒の最上位に与えていました。さすが米どころですね。
静岡県の鑑評会も、「県の鑑評会はあくまで名古屋国税局、全国の鑑評会の予選だ」「いや、県は県独自の基準で選ぶべきだ」等など、これまでいろいろな判断基準で審査されてきました。あくまで内々(静岡県酒造組合)の主催ですから、各組合員(各蔵元)が鑑評会をどう意義付けるかで決まる。順位付けも組合員の総意で決めている。それだけシビアに競い合おうと高い意識で臨んでいるわけです。
飲料・食品・農産物の品質コンペの場合、食味計のような測定器を併用するケースもあるようですが、静岡県清酒鑑評会では機械類を一切使わず、人間のきき酒だけで決めます。10~11人程度の審査員(名古屋国税局鑑定官、大学の醸造学研究者、蔵元代表、杜氏代表など)が官能審査を行い、各出品酒に1点から3点までどれかを付けます。1が優秀、2が普通、3が欠点あり、というシンプルな付け方で、合計で○点以下のものを二次審査、さらに最終審査へと残していきます。
ちなみに1000品近い出品酒を審査する全国新酒鑑評会では、どんなに優秀な審査員でも、香りが強く出る酵母の酒と、おだやかな香りの酒を続けて審査すれば、香りの強い酒を引きずってしまうということで、現在、香りの成分を事前に計測し、審査カテゴリーを分ける、という処置をとっているようです。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
今年の静岡県清酒鑑評会で吟醸の部県知事賞を受賞した喜久醉(藤枝市)、純米の部県知事賞の富士錦(富士宮市)は、ともに原料である米作りから蔵元自ら実践し、一貫した考えで真摯に取り組む蔵元です。
私が主宰するしずおか地酒研究会では、毎年、県の審査員を務める松崎晴雄さん(日本酒評論家)をお招きして審査の内容や新酒の傾向を解説してもらうサロンを開いています。先週4月2日に開催した今年のサロンでは、
「昨夏の猛暑で高温障害を受け、全国的に酒米が硬質で発酵段階で融けにくく、酒造現場では苦労したと聞く。温暖化の影響でこの先も同様の傾向が続くとしたら、融けにくい米にどう対処するかが技術的なポイントになる」
「静岡県の場合、静岡酵母の特性から、元来、硬くひきしまった麹作りが特徴で、発酵も長期低温でじっくり仕込む。米が融けにくい年にはそういうノウハウが生きてくる」
「米の出来に左右されない静岡吟醸のスタイルがしっかり確立されている」
とのことでした。
ちなみに松崎さんは審査にあたって「“静岡らしい酒とは何か”にトコトンこだわって選んだ」とおっしゃっていました。結果を見て「他の審査員も同じ考えだったようだ」と満足されていました。

静岡県清酒鑑評会審査員を務める松崎晴雄さん
酒の鑑評会は、よく、ミスコンテストやF1レースに喩えられることがあります。ミスコンをきっかけに時代時代の女性の美しさが定義され、F1レースを通して自動車メーカーの技術力が見えてくる・・・最上級を競う場にはそれ相応の役割があると思います。
ミスコンやF1のように、川上のトップランナーが仕掛けることは、やがて川下へと大きなうねりとなって波及してくるもの。松崎さんのお話を通して、今後は米に対する蔵元の考え方がますます重要になるな、と実感しました。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
市販酒の品質安定という当初目的から高度な技術競争へと化した酒の鑑評会。「造り手の自己満足にすぎない世界」「米を精米しすぎる吟醸酒は原料を無駄使いするバブリーな酒」と揶揄する声もあるようですが、昔、静岡県の蔵元から聞いた「うちは小さな蔵だが、吟醸酒に挑戦し、技を磨くことで、普通酒も本醸造も純米酒もレベルアップした」という言葉は忘れられません。
また県外の酒の流通業者から「静岡市の繁華街で飲んだとき、高級な料亭や鮨屋ばかりでなく、ごくフツウの居酒屋でも地元の吟醸酒をズラッと並べていた。地方都市ではあまりお目にかかれない。さすが吟醸王国ですね」と言われたことも忘れられません。
日本酒の全国シェアわずか0.7%弱の静岡県が、静岡酵母に続き、日本酒の世界をいかに変革していくか、ほんとうに楽しみです。この春社会人になったみなさんは、とくに、飲まず嫌いせず、静岡の吟醸酒をぜひオーダーし、「素肌美人の酒ですよね」なんてウンチクたれてみてください。先輩や上司から一目置かれるはずですよ!
◆2013年静岡県清酒鑑評会の結果はこちらを。
http://www.shizuoka-sake.jp/prize/h25_report.html
◆松崎晴雄さんによる静岡県清酒鑑評会2013高評については、こちらのブログを。
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2012/04/post_7f89.html
◆5月22日開催予定の全国新酒鑑評会についてはこちらを。
http://www.nrib.go.jp/kan/h24by/info/h24by_info.pdf
なお、「杯は眠らない第3回(≫こちらの記事)」で紹介した酒類総合研究所講演会、今年は5月21日に東広島市民文化センターで開かれます。内容は「なぜ清酒酵母のアルコール発酵は強いのか」「清酒粕の成分調査と機能性成分の安定性について」「古代の酒造り」等など。興味のある方はぜひ!
http://www.nrib.go.jp/kou/49kouen.htm
◆全国新酒鑑評会の入賞酒が一同に集まる一般公開は6月14日に東京池袋サンシャインシティー文化会館で開催されます。誰でも参加できますのでぜひ!
http://www.fullnet.co.jp/zenkoku_shinsyu_kanpyokai/
さらに、全国に流通されている日本酒のうち、静岡県の酒はたったの0.68%。地元なら高いだろうと思ったら県内で流通されている日本酒の中で静岡の酒は20%以下。地酒ファンが憤慨したくなる数字です・・・。確かに気候温暖な静岡県は、酒どころというイメージがないし、すっかり全国区のグルメスポットになった青葉おでん横丁でも、静岡割り(焼酎のお茶割り)は人気だけど、地酒をガンガン飲む客、売る店はありません。
それでも、静岡県内で生産される日本酒は、全国の酒通の間で「吟醸王国」とまで称されるほど人気があるって、信じられますか?
今回は静岡県が吟醸王国になったきっかけともいえる、新酒鑑評会=酒の品質コンテストのディープな世界にご案内しましょう。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
県内の酒蔵は30社ほど。多くは江戸時代に創業した老舗企業です。東海道の宿場町整備によって消費地が形成され、どの町にも必ず造り酒屋があったんですね。中には商才に長けた近江商人が隠密活動の拠点代わりに開業した、なんて蔵もあります。
明治以降は酒税を重要な国税にしようと、国が積極的に酒造業を奨励します。このころ設立されたのが国立の醸造試験所。酒税は国の税収の3割を占めるまでになっていましたが、当時は醸造技術が未熟だったため、品質劣化がしばしば問題になりました。宿場町の酒屋の軒先で量り売りする程度ならまだしも、大量に造って各地へ出荷するとなると品質を安定させなければなりません。税金をあてこんでいる国としても、ちゃんと造ってどんどん売ってもらわないと困るということで、国策で醸造試験所を造り、品質コンテスト=全国新酒鑑評会をスタートさせたのです。
この、全国新酒鑑評会。今年でなんと101回目です。休止したのは戦争中と、「独立行政法人酒類総合研究所」に移行する際に東京から東広島へ施設移転したときだけ。全国規模のコンペティションでこれだけ長く継続し、しかも内容的にも非常にレベルの高い技術コンテストというのは世界でも稀有な存在です。
市販酒の生産拡大のために酒造技術を向上させるという目的でスタートした鑑評会は、やがて蔵元や杜氏にとって、国から優良とのお墨付きをもらい、「金賞」を授与されることはこの上ない誉れとなり、しだいに技術競争の様相を呈してきます。鑑評会の出品用に原料の米を(米の外側は栄養があるが酒にすると雑味になるため)半分以下まで精米し、特別に吟味して醸す、という意味合いの「吟醸酒」は、ここから生まれました。
さまざまな清酒酵母が生まれ、実用化されるようになったのも、鑑評会の功績です。7号酵母、9号酵母といった名称で知られる酵母菌の多くは、鑑評会で好成績だった酒蔵を醸造試験所の技術者が調査し、酵母を収集し、保存・育種して普及させました。優良な酵母を選抜して安全な環境で培養し、全国の酒蔵へ頒布することは、日本酒全体の品質安定につながったのです。
現在、酵母は、日本醸造協会という業界団体が専門に培養しており、実用化した順に番号を付けています。現役の協会酵母で最も古いのは6号酵母で、大正時代に秋田の「新政」という蔵から採取されました。7号酵母は昭和21年に長野の「真澄」から。9号酵母は熊本の「香露」から出た香りの高い酵母で、吟醸酒向けに一世風靡しました。みなさんがイメージする吟醸酒のフルーティーな香りは、9号酵母が定着させたとも言われ、今でも鑑評会出品酒の多くは9号系統の酵母を使用しているようです。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
さて、静岡県。東海道の城下町を中心に、個人経営の小規模な蔵が多かったものの、交通の要所=安定した消費地という地理的条件に支えられ、そこそこ繁盛していました。しかしながら、太平洋戦争中は原料米不足の折から統廃合を余儀なくされ、生き残った蔵も、東海道線、国道1号線、東名高速道路という新たな交通の動脈が物流を加速させ、高度成長期には全国の銘醸地からさまざまな酒が流入し、地酒は存在感を失っていきます。日本酒の生産量のピークは昭和48年頃と言われていますが、静岡県の蔵元は昭和50年代前半頃まで灘や伏見の大手酒造会社の下請けで生計を立てるなど“日陰の時代”が続きました。
昭和50年代後半から下請けの量が減り始め、さらに経営が苦しくなった県内の蔵元は、それまで経営の柱には考えなかった「吟醸酒」で生き残りを図る英断をします。
この時に追い風となったのが静岡酵母。蔵元に技術指導をしていた静岡県工業技術センターの河村傅兵衛氏が、蔵元が自立するには他地域の亜流にならず、独自スタイルで勝負すべきと考え、吟醸酒造りの実績を持つ県内の蔵で発見した酵母菌をもとに、バイオテクノロジーを駆使して独自開発したものです。
昭和61年の全国新酒鑑評会には、県内から21銘柄が出品し、金賞10、銀賞7を獲得しました。入賞率は実に87%。2位石川県、3位福井県をおさえて全国一位という、県酒造史始まって以来の快挙を成し遂げました。
この年、全国新酒鑑評会に出品された酒は800銘柄ほどで、うち約100銘柄が金賞に選ばれたのですが、この中の10銘柄を静岡県が占めたのです。しかも9号酵母ではなく、地方研究機関が独自に開発した酵母による吟醸酒造り。酒どころとしては無名だった静岡県は、この年の鑑評会を機に、一躍、銘醸地に名乗りを上げたのでした。
他県の研究機関や蔵元は驚愕し、静岡酵母に着目します。「静岡で成功するなら当県だって・・・」と各県の酵母開発に勢いが付き、優良酵母の輩出県だった秋田や長野も新たに独自酵母を生み出します。長野県の「アルプス酵母」は、繊細でまるみのあるおだやかな香りの静岡酵母の酒とは異なる、香り華やかで濃厚な酒を醸し出し、その後の鑑評会で大量入賞しました。静岡酵母の酒が、薄化粧の素肌美人だとしたら、アルプス酵母は完璧な女優メイクを施した美女って感じでしょうか。
いずれにしても、静岡県が先鞭を付けた酵母開発と吟醸酒造りの技術革新は、それまで、国の指導による“鑑評会出品酒”の規格に、新たな地方化・個性化の波をもたらしたのでした。“美女の条件”は画一じゃなくなったってことですね!
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
全国新酒鑑評会は毎年5月に行われます。その前に、地域国税局単位の新酒鑑評会が4月(静岡県は東海4県を管轄する名古屋国税局に所属・現在は秋に開催)、県単位の鑑評会が3月に開かれます。
静岡県清酒鑑評会は、吟醸酒の部・純米酒の部と2つ部門があり、点数を付けて順位を決め、最上位の銘柄に県知事賞を授与します。順位を発表している県はあまり多くありません。
2012年全国新酒鑑評会(東広島市アリーナ)
2013年静岡県清酒鑑評会一般公開(グランディエールブケトーカイ)
各県でどういう酒に県知事賞を与えるかはさまざまです。私が以前、取材に行った宮城県清酒鑑評会は、県知事賞は宮城県の米を使った酒の最上位に与えていました。さすが米どころですね。
静岡県の鑑評会も、「県の鑑評会はあくまで名古屋国税局、全国の鑑評会の予選だ」「いや、県は県独自の基準で選ぶべきだ」等など、これまでいろいろな判断基準で審査されてきました。あくまで内々(静岡県酒造組合)の主催ですから、各組合員(各蔵元)が鑑評会をどう意義付けるかで決まる。順位付けも組合員の総意で決めている。それだけシビアに競い合おうと高い意識で臨んでいるわけです。
飲料・食品・農産物の品質コンペの場合、食味計のような測定器を併用するケースもあるようですが、静岡県清酒鑑評会では機械類を一切使わず、人間のきき酒だけで決めます。10~11人程度の審査員(名古屋国税局鑑定官、大学の醸造学研究者、蔵元代表、杜氏代表など)が官能審査を行い、各出品酒に1点から3点までどれかを付けます。1が優秀、2が普通、3が欠点あり、というシンプルな付け方で、合計で○点以下のものを二次審査、さらに最終審査へと残していきます。
ちなみに1000品近い出品酒を審査する全国新酒鑑評会では、どんなに優秀な審査員でも、香りが強く出る酵母の酒と、おだやかな香りの酒を続けて審査すれば、香りの強い酒を引きずってしまうということで、現在、香りの成分を事前に計測し、審査カテゴリーを分ける、という処置をとっているようです。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
今年の静岡県清酒鑑評会で吟醸の部県知事賞を受賞した喜久醉(藤枝市)、純米の部県知事賞の富士錦(富士宮市)は、ともに原料である米作りから蔵元自ら実践し、一貫した考えで真摯に取り組む蔵元です。
私が主宰するしずおか地酒研究会では、毎年、県の審査員を務める松崎晴雄さん(日本酒評論家)をお招きして審査の内容や新酒の傾向を解説してもらうサロンを開いています。先週4月2日に開催した今年のサロンでは、
「昨夏の猛暑で高温障害を受け、全国的に酒米が硬質で発酵段階で融けにくく、酒造現場では苦労したと聞く。温暖化の影響でこの先も同様の傾向が続くとしたら、融けにくい米にどう対処するかが技術的なポイントになる」
「静岡県の場合、静岡酵母の特性から、元来、硬くひきしまった麹作りが特徴で、発酵も長期低温でじっくり仕込む。米が融けにくい年にはそういうノウハウが生きてくる」
「米の出来に左右されない静岡吟醸のスタイルがしっかり確立されている」
とのことでした。
ちなみに松崎さんは審査にあたって「“静岡らしい酒とは何か”にトコトンこだわって選んだ」とおっしゃっていました。結果を見て「他の審査員も同じ考えだったようだ」と満足されていました。
静岡県清酒鑑評会審査員を務める松崎晴雄さん
酒の鑑評会は、よく、ミスコンテストやF1レースに喩えられることがあります。ミスコンをきっかけに時代時代の女性の美しさが定義され、F1レースを通して自動車メーカーの技術力が見えてくる・・・最上級を競う場にはそれ相応の役割があると思います。
ミスコンやF1のように、川上のトップランナーが仕掛けることは、やがて川下へと大きなうねりとなって波及してくるもの。松崎さんのお話を通して、今後は米に対する蔵元の考え方がますます重要になるな、と実感しました。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇
市販酒の品質安定という当初目的から高度な技術競争へと化した酒の鑑評会。「造り手の自己満足にすぎない世界」「米を精米しすぎる吟醸酒は原料を無駄使いするバブリーな酒」と揶揄する声もあるようですが、昔、静岡県の蔵元から聞いた「うちは小さな蔵だが、吟醸酒に挑戦し、技を磨くことで、普通酒も本醸造も純米酒もレベルアップした」という言葉は忘れられません。
また県外の酒の流通業者から「静岡市の繁華街で飲んだとき、高級な料亭や鮨屋ばかりでなく、ごくフツウの居酒屋でも地元の吟醸酒をズラッと並べていた。地方都市ではあまりお目にかかれない。さすが吟醸王国ですね」と言われたことも忘れられません。
日本酒の全国シェアわずか0.7%弱の静岡県が、静岡酵母に続き、日本酒の世界をいかに変革していくか、ほんとうに楽しみです。この春社会人になったみなさんは、とくに、飲まず嫌いせず、静岡の吟醸酒をぜひオーダーし、「素肌美人の酒ですよね」なんてウンチクたれてみてください。先輩や上司から一目置かれるはずですよ!
◆2013年静岡県清酒鑑評会の結果はこちらを。
http://www.shizuoka-sake.jp/prize/h25_report.html
◆松崎晴雄さんによる静岡県清酒鑑評会2013高評については、こちらのブログを。
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2012/04/post_7f89.html
◆5月22日開催予定の全国新酒鑑評会についてはこちらを。
http://www.nrib.go.jp/kan/h24by/info/h24by_info.pdf
なお、「杯は眠らない第3回(≫こちらの記事)」で紹介した酒類総合研究所講演会、今年は5月21日に東広島市民文化センターで開かれます。内容は「なぜ清酒酵母のアルコール発酵は強いのか」「清酒粕の成分調査と機能性成分の安定性について」「古代の酒造り」等など。興味のある方はぜひ!
http://www.nrib.go.jp/kou/49kouen.htm
◆全国新酒鑑評会の入賞酒が一同に集まる一般公開は6月14日に東京池袋サンシャインシティー文化会館で開催されます。誰でも参加できますのでぜひ!
http://www.fullnet.co.jp/zenkoku_shinsyu_kanpyokai/
Posted by 日刊いーしず at 12:00


