2013年04月26日
第7回 酔読ノススメ
当コラム第3回「17歳の酒縁」(≫こちら)で紹介した、『喜久醉純米大吟醸松下米』の原料米生産農家・松下明弘さんが、【ロジカルな田んぼ】(日経プレミアシリーズ)という新書本を上梓しました。
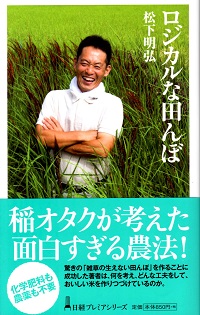
独学で辿り着いた〈農薬や化学肥料を使わないのに雑草が生えなくなった田んぼづくり〉のプロセスを通し、農作業のすべてに理由があることを、学者の論説ではなく自称稲オタクとして実証したもの。〈有機農業〉の本意や、「17歳の酒縁」でも触れた喜久醉の蔵元との出会い、巨大胚芽米カミアカリを育種した経緯など等、農業者自身がここまでクレバーに語り切るなんて、ニッポン農業は新しい次元に進化したんじゃないかと感じさせる筆力です。たまたま発刊直後の4月12日、所用で上京して新宿紀伊国屋書店の新刊本コーナーをのぞいたら、名だたるベストセラーと並んでセンターポジションに堂々と並んでいて、胸が熱くなりました。
2000年10月、藤枝市出身の写真家多々良栄里さんが、松下さんを密着撮影した連作「松下君の山田錦」(土門拳文化奨励賞受賞)を新宿コニカプラザで展示披露した際、松下さんと2人で観に行き、本屋に寄りたいと言う彼につきあって、新宿紀伊国屋書店で長々時間をつぶしたことがありました。本などに頼らず、トコトン現場・実践主義を貫く人だと思っていた彼が専門書を漁っている姿に、少々意外な感じがしましたが、こうして、この書店の新刊センターポジションに著作を並べてしまう日が来るとは・・・。
今回は【ロジカルな田んぼ】が加わったMY書棚から、読むだけで心地よく酔いそうな、お気に入り本をご紹介します。

桜木廂夫さんの【名酒発掘の旅】(平凡社/1987年刊)は、私が地酒の取材を始めて最初に購入したガイド本でした。「傳魚坊」「笹舟」「松島」等と並び、地酒を育てた料飲店として名高い神田「一ノ茶屋」店主が綴った酒蔵訪問記で、静岡県では『春の甍』という酒が紹介されています。ピンと来ない人も多いでしょう。これ、藤枝の『志太泉』が当時、首都圏向けに発売していた純米酒ブランドです。久しぶりに読み返して気がついたんですが、桜木さんは「この酒蔵に今期、一升瓶で五千本の純米酒を注文している」と書いています。個人店一店の注文数か!?と目を疑いましたが、当時はこういう個店が、地方の隠れた名酒を買い支えていたんだなあと感慨深くなりました。
それはさておき、桜木さんは、当時の志太泉の杜氏が、桜木さんの常識を超える洗米作業と麹造りをしていたこと、若い酒造技術者が熱心に指導している光景を紹介しています。ピンと来る人もいるでしょう。杜氏は多田信男さん。今は磯自慢の杜氏さんです。若い技術者というのは静岡県工業技術センター(当時)で静岡酵母を開発した河村傳兵衛さんで、多田さんと同い年の43歳。お二人ともバリバリの働き盛りでした。
桜木さんが、静岡酵母や酒造りの技術全般について質問しても、河村さんからは判で押したように「酵母だけでは名酒はできない」「酵母より麹のほうが大切」「しっかりした麹を造らないといけません」と返ってきます。とりわけ印象的だったのは、「(河村氏は)麹造りは建築で言うならば、土台であり骨組みだと言った。酵母の役割は内装であり、外装であり、いわばインテリアの部分に属する、とも言った」という一節です。酒の勉強を始めたばかりの若輩者にとって、麹と酵母¬=2大微生物の働きや役割を正しく理解することは最初の大きな関門。これをすんなり通過させてくれたバイパスのような一節でした。
この本は、志太泉さんや河村さんに薦められたわけではなく、書店でたまたま見つけ、静岡の蔵が載っている数少ない本だったのでとりあえず買ってみたんですが、その後に出会った酒の関係者の中で「麹造りの重要性をしっかり語れる人」とそうではない人では、物事の本質を語っているのか、そもそも本質を理解しているかが、なんとなく見えてきました。
酒に限りません。料理人ならダシ、農家なら土づくり、企業経営者なら基本となるシステムづくりや人員配置・・・。インタビューでグッと心を掴まされるのは、こういう話を、時間を割いて語る人です。基礎の土台をしっかり作ることに手を抜かず、真摯に取り組む人、ですね。最初に読んだ酒の本で、土台というキーワードで酒造りの核心を突いた一節に出会えたというのは、私の取材活動にとって実に大きかった。
この本を買った直後に、河村さんから「よかったら読んでみてください」と薦められたのがこの本でした(笑)。そのときの、照れくさそうな表情を、昨日のことのように覚えています。

藤田千恵子さんの【杜氏という仕事】(新潮新書/2004年刊)は、自分もいつか、酒の分野でこういうものが書けるようになりたいと具体的にイメージできた本です。著者の藤田さんも、こういうライターになりたいと思わせる憧れの女性。何度かお会いし、しずおか地酒研究会で講演に来ていただいたこともあります。とても面白い講演&蔵元セッションだったので、よかったらこちらをご覧ください。
◆藤田さんの講演
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2008/04/post_1c05.html
◆藤田さんvs國香・杉錦・志太泉・喜久醉トークセッション
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2008/04/vs_4edd.html
本書は、滋賀県の銘酒『喜楽長』を醸す能登杜氏・天保正一さんのロングインタビューを柱に、杜氏という日本の伝統的な技能者の職業観や人生観、日本酒の造り手が置かれた環境や酒造業の未来について、じっくり読ませてくれます。
この本にもお気に入りの一節があります。
「杜氏はね、眠れん夜があるものですよ。(中略)酒造りの責任者には、孤独なところもあるのですよ。でも、その責任で苦労する部分と、自分の技術で対応していくおもしろみと、両方を味わうようにならないと、杜氏はだめですね。結局、酒造りというのは、何年やっても、これでいい、ということがない。去年どおりでもだめなんです。(中略)自分の理想通りには、なかなか進まない。その面だけ孤独なんですよ」。
名人と謳われる職人が〈孤独〉という言葉を吐く・・・このことの重さが、モノづくりの取材をしていく上でいつも脳裏に甦ってきます。
文中、天保さんに憧れ、蔵元・喜多酒造に直談判して蔵人になった西原光志さんという若者が登場します。ピンと来る人もいると思いますが、今、西原さんは、『志太泉』の杜氏を務めています。なんとも不思議な酒縁ですよね。

吉田健一さんの【まろやかな日本】(新潮社/1978年刊)は、発刊年は前2冊よりも古いのですが、出会ったのは2年前。しずおか地酒研究会で企画した『酒と匠の文化祭』というイベントの中で、フリーアナウンサー國本良博さんに酒の本の朗読をお願いした中の一冊です。朗読会の様子はこちらをご覧ください。
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_ea42.html
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_2948.html
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_3123.html
國本さんにはこのとき、井伏鱒二や若山牧水の歌、篠田次郎さんの酒の歳時記、不肖私の県内酒蔵レポート等を読んでもらったのですが、せっかくプロのアナウンサーに頼むなら、読むのはしんどいけど心地よい朗読なら多少は耳に入るかも・・・という、ちょっと高尚な酒文化論も入れようと思い、あれこれ探して発掘しました。
著者の吉田さんは、昭和の宰相吉田茂のご長男。英国タイムズ紙に「完全無比な英語を使いこなす日本の英文学者」と紹介された人で、本書は1974年、イギリスで「Japan is a circle」というタイトルで出版され、吉田さんが亡くなった1年後に日本で翻訳・出版された日本文化論です。全26章のうち、日本酒について4章が費やされており、何度も読み込んでワードのテキストに入力し、國本さんと相談して音読に適さない部分をカットし、朗読用台本に仕上げました。一部を再掲します。
「日本酒というものの絶妙さは、飲んでみなければとうてい信じられるものではない。多くの要素が、といっても量ではなく、質の点で入り組んだ日本の食事には、1回の献立のなかに胡桃から鶉や熊の足といったものまで含まれている場合もありうるが、日本酒はその全部と合う。
ある人が一度、日本酒でビフテキを食べたことがあって、これも申し分なく合ったらしい。しかしむろん、何を一緒に食べようと、そんなことは酒自体に比べればほとんど問題にならない。この点で日本酒は葡萄酒に優るのであって、全然何も食べないか、せいぜい塩をちょっと舐める程度でもすむ。つまり、いい酒ができるのに役立っている複雑な成分がそこにあれば、あとはただ盃を口へ運ぶこと以外、現実には何一つしないで充分だということである。
日本酒はほとんど、どんな食べ物とも合うだけでなく、それ自体、ほとんど、どんなものにも成り得る。西洋ではどの国だろうと人は大理石の大広間でシャンパンを飲み、安酒場でジンを飲む。日本では、同じ日本酒を、金箔で飾り立てた豪華な座敷で飲むこともあれば、馬方が出入りする道端の小さな屋台で、縁に少しばかり塩をのせた四角い杉材の容器に入れて飲むこともある。
日本酒が、そうした屋台でのほうがかえっていい状態に保たれていることさえあるかもしれないのは、少なくとも上流階級よりも馬方のほうが自分たちの飲むものに気を配るからであって、少なくともそういう階級が存在していた頃はそうだった。」(第15章「日本酒の定義」より抜粋)。
英語の翻訳文で朗読しづらい表現が多かったにもかかわらず、國本さんの艶やかで抑揚のある声によって、吉田さん自身が、新橋あたりのガード下の飲み屋を恋しく思い浮かべ、ロンドンのセレブたちに滔々と語って聞かせている・・・そんな情景が浮かんできました。呑みながら聴くっていうのが、またいいんですよねえ。
國本さんは、しずおか地酒研究会設立のきっかけとなった、1995年の静岡市南部図書館地酒講座のプログラムに、地酒エッセイの寄稿をお願いして以来のおつきあい。エッセイを頼んだきっかけは、國本さんがラジオ番組で河村傳兵衛さんにインタビューしていたのを偶然聴いて、とても面白くて、静岡新聞社の知り合いに仲介を頼んだのです。その後、それまで日本酒を敬遠していた國本さんを、無事、こちら側?に寝返させることが出来ました(笑)。
日本酒の朗読ライブは、國本さんと私のライフワークにできればいいなあと思っています。

2010年12月、大旅籠柏屋(岡部)で開催した「酒と匠の文化祭」での國本良博さんの酒の朗読会
新宿紀伊国屋で【ロジカルな田んぼ】を購入した日の夜、広尾の日赤通りにある定食店『一汁三菜』で、喜久醉純米吟醸松下米と、カミアカリ(松下さんが育種した巨大胚芽米)の玄米ご飯を味わいました。松下さんの米をこよなく愛する店主の朝川佳子さんと、本の話や喜久醉の県知事賞受賞の話題でひとしきり盛り上がりました。
【ロジカルな田んぼ】でお気に入りの一節は、
「自然の摂理にさからわないこと。さまざまな生きものの有機的つながりをこわさないよう、人間も自然の摂理のなかで動くこと」「田んぼの持ち主は松下になっているけれど、決して私一人のものじゃない。多くの生きものの生活の場になっている。そこで産まれ、そこで育ち、そこで死に、その死骸がまた田んぼの栄養になっていく。こうした循環から、少しだけおすそ分けをもらうのが有機農業だと思うのです」(92~93ページ)。
ここを読むと、ふと、禅の教えが浮かんでくるのです。無我の境地とは、田んぼの中の微生物のように、有機的つながりに身をゆだねるということだろう、と、腑に落ちる。
私は年に数回、京都の禅寺に坐禅をしに行きます。無我になろうと意識するうちは、なかなかなれないんですが、和尚から薦められた盛永宗興さん(元・妙心寺塔頭大珠院住職)の【お前は誰か】(禅文化研究所/2005年刊)に、こんな一節があります。

「DNAは生物の最も基本的な内在情報であって、細胞が一箇しかない単細胞生物から、人間のように数兆規模の細胞を持つ多細胞生物にいたるまで、例外なく共通に持っている物質です。(中略)すべてに共通して含まれるということ、この意味で、普遍的な〈いのち〉と、多様性を持った種種雑多な存在が、実は一つであるといえる。岡田博士は「一即多多即一」という仏教的な概念を、生物学の立場からお話された」。
岡田博士というのは、盛永さんが学長を務めた花園大学の文化祭に講師で招いた発生生物学の世界的権威・岡田節人博士のこと。評論家立花隆さんと脳死について対談したNHKの番組を盛永さんがご覧になり、講師に招かれたようです。
松下さんの田んぼは、宇宙にも喩えられる般若心経の世界を具現化したものではないか・・・。彼の山田錦で醸した酒と、玄米カミアカリを咀嚼していると、そんな妄想にとらわれてしまいます。
酒に関係のない話に飛んでいきそうなので、このへんで杯を眠らせておきますが、古い本でもネットで取り寄せられる便利な時代になりましたので、興味があったら読んでみてください。ちなみに【ロジカルな田んぼ】、東京の有名書店ではセンターポジションなのに、静岡の書店ではとんと見かけません。かつての静岡地酒と同じ扱いですね(苦笑)。・・・静岡の書店の奮起に期待します!
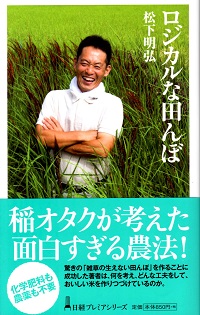
独学で辿り着いた〈農薬や化学肥料を使わないのに雑草が生えなくなった田んぼづくり〉のプロセスを通し、農作業のすべてに理由があることを、学者の論説ではなく自称稲オタクとして実証したもの。〈有機農業〉の本意や、「17歳の酒縁」でも触れた喜久醉の蔵元との出会い、巨大胚芽米カミアカリを育種した経緯など等、農業者自身がここまでクレバーに語り切るなんて、ニッポン農業は新しい次元に進化したんじゃないかと感じさせる筆力です。たまたま発刊直後の4月12日、所用で上京して新宿紀伊国屋書店の新刊本コーナーをのぞいたら、名だたるベストセラーと並んでセンターポジションに堂々と並んでいて、胸が熱くなりました。
2000年10月、藤枝市出身の写真家多々良栄里さんが、松下さんを密着撮影した連作「松下君の山田錦」(土門拳文化奨励賞受賞)を新宿コニカプラザで展示披露した際、松下さんと2人で観に行き、本屋に寄りたいと言う彼につきあって、新宿紀伊国屋書店で長々時間をつぶしたことがありました。本などに頼らず、トコトン現場・実践主義を貫く人だと思っていた彼が専門書を漁っている姿に、少々意外な感じがしましたが、こうして、この書店の新刊センターポジションに著作を並べてしまう日が来るとは・・・。
今回は【ロジカルな田んぼ】が加わったMY書棚から、読むだけで心地よく酔いそうな、お気に入り本をご紹介します。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

桜木廂夫さんの【名酒発掘の旅】(平凡社/1987年刊)は、私が地酒の取材を始めて最初に購入したガイド本でした。「傳魚坊」「笹舟」「松島」等と並び、地酒を育てた料飲店として名高い神田「一ノ茶屋」店主が綴った酒蔵訪問記で、静岡県では『春の甍』という酒が紹介されています。ピンと来ない人も多いでしょう。これ、藤枝の『志太泉』が当時、首都圏向けに発売していた純米酒ブランドです。久しぶりに読み返して気がついたんですが、桜木さんは「この酒蔵に今期、一升瓶で五千本の純米酒を注文している」と書いています。個人店一店の注文数か!?と目を疑いましたが、当時はこういう個店が、地方の隠れた名酒を買い支えていたんだなあと感慨深くなりました。
それはさておき、桜木さんは、当時の志太泉の杜氏が、桜木さんの常識を超える洗米作業と麹造りをしていたこと、若い酒造技術者が熱心に指導している光景を紹介しています。ピンと来る人もいるでしょう。杜氏は多田信男さん。今は磯自慢の杜氏さんです。若い技術者というのは静岡県工業技術センター(当時)で静岡酵母を開発した河村傳兵衛さんで、多田さんと同い年の43歳。お二人ともバリバリの働き盛りでした。
桜木さんが、静岡酵母や酒造りの技術全般について質問しても、河村さんからは判で押したように「酵母だけでは名酒はできない」「酵母より麹のほうが大切」「しっかりした麹を造らないといけません」と返ってきます。とりわけ印象的だったのは、「(河村氏は)麹造りは建築で言うならば、土台であり骨組みだと言った。酵母の役割は内装であり、外装であり、いわばインテリアの部分に属する、とも言った」という一節です。酒の勉強を始めたばかりの若輩者にとって、麹と酵母¬=2大微生物の働きや役割を正しく理解することは最初の大きな関門。これをすんなり通過させてくれたバイパスのような一節でした。
この本は、志太泉さんや河村さんに薦められたわけではなく、書店でたまたま見つけ、静岡の蔵が載っている数少ない本だったのでとりあえず買ってみたんですが、その後に出会った酒の関係者の中で「麹造りの重要性をしっかり語れる人」とそうではない人では、物事の本質を語っているのか、そもそも本質を理解しているかが、なんとなく見えてきました。
酒に限りません。料理人ならダシ、農家なら土づくり、企業経営者なら基本となるシステムづくりや人員配置・・・。インタビューでグッと心を掴まされるのは、こういう話を、時間を割いて語る人です。基礎の土台をしっかり作ることに手を抜かず、真摯に取り組む人、ですね。最初に読んだ酒の本で、土台というキーワードで酒造りの核心を突いた一節に出会えたというのは、私の取材活動にとって実に大きかった。
この本を買った直後に、河村さんから「よかったら読んでみてください」と薦められたのがこの本でした(笑)。そのときの、照れくさそうな表情を、昨日のことのように覚えています。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

藤田千恵子さんの【杜氏という仕事】(新潮新書/2004年刊)は、自分もいつか、酒の分野でこういうものが書けるようになりたいと具体的にイメージできた本です。著者の藤田さんも、こういうライターになりたいと思わせる憧れの女性。何度かお会いし、しずおか地酒研究会で講演に来ていただいたこともあります。とても面白い講演&蔵元セッションだったので、よかったらこちらをご覧ください。
◆藤田さんの講演
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2008/04/post_1c05.html
◆藤田さんvs國香・杉錦・志太泉・喜久醉トークセッション
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2008/04/vs_4edd.html
本書は、滋賀県の銘酒『喜楽長』を醸す能登杜氏・天保正一さんのロングインタビューを柱に、杜氏という日本の伝統的な技能者の職業観や人生観、日本酒の造り手が置かれた環境や酒造業の未来について、じっくり読ませてくれます。
この本にもお気に入りの一節があります。
「杜氏はね、眠れん夜があるものですよ。(中略)酒造りの責任者には、孤独なところもあるのですよ。でも、その責任で苦労する部分と、自分の技術で対応していくおもしろみと、両方を味わうようにならないと、杜氏はだめですね。結局、酒造りというのは、何年やっても、これでいい、ということがない。去年どおりでもだめなんです。(中略)自分の理想通りには、なかなか進まない。その面だけ孤独なんですよ」。
名人と謳われる職人が〈孤独〉という言葉を吐く・・・このことの重さが、モノづくりの取材をしていく上でいつも脳裏に甦ってきます。
文中、天保さんに憧れ、蔵元・喜多酒造に直談判して蔵人になった西原光志さんという若者が登場します。ピンと来る人もいると思いますが、今、西原さんは、『志太泉』の杜氏を務めています。なんとも不思議な酒縁ですよね。
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

吉田健一さんの【まろやかな日本】(新潮社/1978年刊)は、発刊年は前2冊よりも古いのですが、出会ったのは2年前。しずおか地酒研究会で企画した『酒と匠の文化祭』というイベントの中で、フリーアナウンサー國本良博さんに酒の本の朗読をお願いした中の一冊です。朗読会の様子はこちらをご覧ください。
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_ea42.html
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_2948.html
http://mayumi-s-jizake.blogzine.jp/blog/2010/12/5_3123.html
國本さんにはこのとき、井伏鱒二や若山牧水の歌、篠田次郎さんの酒の歳時記、不肖私の県内酒蔵レポート等を読んでもらったのですが、せっかくプロのアナウンサーに頼むなら、読むのはしんどいけど心地よい朗読なら多少は耳に入るかも・・・という、ちょっと高尚な酒文化論も入れようと思い、あれこれ探して発掘しました。
著者の吉田さんは、昭和の宰相吉田茂のご長男。英国タイムズ紙に「完全無比な英語を使いこなす日本の英文学者」と紹介された人で、本書は1974年、イギリスで「Japan is a circle」というタイトルで出版され、吉田さんが亡くなった1年後に日本で翻訳・出版された日本文化論です。全26章のうち、日本酒について4章が費やされており、何度も読み込んでワードのテキストに入力し、國本さんと相談して音読に適さない部分をカットし、朗読用台本に仕上げました。一部を再掲します。
「日本酒というものの絶妙さは、飲んでみなければとうてい信じられるものではない。多くの要素が、といっても量ではなく、質の点で入り組んだ日本の食事には、1回の献立のなかに胡桃から鶉や熊の足といったものまで含まれている場合もありうるが、日本酒はその全部と合う。
ある人が一度、日本酒でビフテキを食べたことがあって、これも申し分なく合ったらしい。しかしむろん、何を一緒に食べようと、そんなことは酒自体に比べればほとんど問題にならない。この点で日本酒は葡萄酒に優るのであって、全然何も食べないか、せいぜい塩をちょっと舐める程度でもすむ。つまり、いい酒ができるのに役立っている複雑な成分がそこにあれば、あとはただ盃を口へ運ぶこと以外、現実には何一つしないで充分だということである。
日本酒はほとんど、どんな食べ物とも合うだけでなく、それ自体、ほとんど、どんなものにも成り得る。西洋ではどの国だろうと人は大理石の大広間でシャンパンを飲み、安酒場でジンを飲む。日本では、同じ日本酒を、金箔で飾り立てた豪華な座敷で飲むこともあれば、馬方が出入りする道端の小さな屋台で、縁に少しばかり塩をのせた四角い杉材の容器に入れて飲むこともある。
日本酒が、そうした屋台でのほうがかえっていい状態に保たれていることさえあるかもしれないのは、少なくとも上流階級よりも馬方のほうが自分たちの飲むものに気を配るからであって、少なくともそういう階級が存在していた頃はそうだった。」(第15章「日本酒の定義」より抜粋)。
英語の翻訳文で朗読しづらい表現が多かったにもかかわらず、國本さんの艶やかで抑揚のある声によって、吉田さん自身が、新橋あたりのガード下の飲み屋を恋しく思い浮かべ、ロンドンのセレブたちに滔々と語って聞かせている・・・そんな情景が浮かんできました。呑みながら聴くっていうのが、またいいんですよねえ。
國本さんは、しずおか地酒研究会設立のきっかけとなった、1995年の静岡市南部図書館地酒講座のプログラムに、地酒エッセイの寄稿をお願いして以来のおつきあい。エッセイを頼んだきっかけは、國本さんがラジオ番組で河村傳兵衛さんにインタビューしていたのを偶然聴いて、とても面白くて、静岡新聞社の知り合いに仲介を頼んだのです。その後、それまで日本酒を敬遠していた國本さんを、無事、こちら側?に寝返させることが出来ました(笑)。
日本酒の朗読ライブは、國本さんと私のライフワークにできればいいなあと思っています。
2010年12月、大旅籠柏屋(岡部)で開催した「酒と匠の文化祭」での國本良博さんの酒の朗読会
◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇
新宿紀伊国屋で【ロジカルな田んぼ】を購入した日の夜、広尾の日赤通りにある定食店『一汁三菜』で、喜久醉純米吟醸松下米と、カミアカリ(松下さんが育種した巨大胚芽米)の玄米ご飯を味わいました。松下さんの米をこよなく愛する店主の朝川佳子さんと、本の話や喜久醉の県知事賞受賞の話題でひとしきり盛り上がりました。
【ロジカルな田んぼ】でお気に入りの一節は、
「自然の摂理にさからわないこと。さまざまな生きものの有機的つながりをこわさないよう、人間も自然の摂理のなかで動くこと」「田んぼの持ち主は松下になっているけれど、決して私一人のものじゃない。多くの生きものの生活の場になっている。そこで産まれ、そこで育ち、そこで死に、その死骸がまた田んぼの栄養になっていく。こうした循環から、少しだけおすそ分けをもらうのが有機農業だと思うのです」(92~93ページ)。
ここを読むと、ふと、禅の教えが浮かんでくるのです。無我の境地とは、田んぼの中の微生物のように、有機的つながりに身をゆだねるということだろう、と、腑に落ちる。
私は年に数回、京都の禅寺に坐禅をしに行きます。無我になろうと意識するうちは、なかなかなれないんですが、和尚から薦められた盛永宗興さん(元・妙心寺塔頭大珠院住職)の【お前は誰か】(禅文化研究所/2005年刊)に、こんな一節があります。

「DNAは生物の最も基本的な内在情報であって、細胞が一箇しかない単細胞生物から、人間のように数兆規模の細胞を持つ多細胞生物にいたるまで、例外なく共通に持っている物質です。(中略)すべてに共通して含まれるということ、この意味で、普遍的な〈いのち〉と、多様性を持った種種雑多な存在が、実は一つであるといえる。岡田博士は「一即多多即一」という仏教的な概念を、生物学の立場からお話された」。
岡田博士というのは、盛永さんが学長を務めた花園大学の文化祭に講師で招いた発生生物学の世界的権威・岡田節人博士のこと。評論家立花隆さんと脳死について対談したNHKの番組を盛永さんがご覧になり、講師に招かれたようです。
松下さんの田んぼは、宇宙にも喩えられる般若心経の世界を具現化したものではないか・・・。彼の山田錦で醸した酒と、玄米カミアカリを咀嚼していると、そんな妄想にとらわれてしまいます。
酒に関係のない話に飛んでいきそうなので、このへんで杯を眠らせておきますが、古い本でもネットで取り寄せられる便利な時代になりましたので、興味があったら読んでみてください。ちなみに【ロジカルな田んぼ】、東京の有名書店ではセンターポジションなのに、静岡の書店ではとんと見かけません。かつての静岡地酒と同じ扱いですね(苦笑)。・・・静岡の書店の奮起に期待します!
Posted by 日刊いーしず at 12:00


