2013年06月28日
第11回 世界遺産の仕込み水
富士山が世界文化遺産に登録されましたね。世界遺産登録運動については、かれこれ10年ぐらい取材し続け、主に県の広報誌や中日新聞の広告企画特集等で記事を書いてきました。この間、「えっ、富士山って世界遺産じゃなかったの?」と驚く人や、「あれだけ麓が都市開発されちゃって、ゴミの不法投棄や山小屋のし尿が問題になっているんだから、世界遺産なんて無理無理」な~んて冷めた人の声もよく聞きました。
5月末にユネスコの諮問機関(イコモス)の評価が出てからは、「最初から自然遺産ではなく、文化遺産登録を目指せば、もっと登録は早かった」という関係者の声が印象に残っています。やっぱり文化の力って偉大なんですね。

2013年1月1日、家族で初詣した三保松原
文化遺産に登録されたとしても、富士山の場合、文化を育んだ自然を保護していくことも重要です。以前、富士山の水の恵みをテーマに、こんな記事を書きました。
湧水に育まれるニジマス養殖
『白糸の滝』の北、芝川の上流に広がる『猪之頭湧水群』はニジマス養殖で知られる。昭和11年に静岡県水産試験場富士養鱒場が設立したのを機に、猪之頭一帯で養殖池が作られ、一大養鱒地に。戦後は冷凍ニジマスが北米に輸出され、国内需要も右肩上がりに伸びた。
産業は成長・発展とともにリスクも伴う。台風や水害等の影響でしばしば変化する湧水量。加えて高度成長期には周辺に工場や事業所が進出し、水量は相対的に減少し始めた。リスクを避けた養鱒業者は市外・県外へ移転し、川魚消費の伸び悩みも手伝って、現在、猪之頭の養鱒業者は30軒足らずとなった。
柿島養鱒の岩本いづみ社長は、ニジマス本来の美味しさを見直してもらおうと、飼料添加物や人工色素に頼らない天然素材の餌を毎日作って与える。3児の母でもある岩本社長の考えは「色素を添加した、脂肪が不自然に多い魚は育てたくない」と明快。餌の自家製造は養鱒業では極めて珍しいという。
「魚が川の中で長い時間をかけ、自然に育つ環境を再現したい。それには豊富な流水量が不可欠」と案内してくれたのは、養殖池のすぐそばにある湧水ポイント。猪之頭はかつて「井之頭」と表記されていたそうだが、その名を象徴するような滝が水のカーテンのように岩肌を厚く覆い、川の各所で水がボコボコと湧き上がっている。今では国内外の名のある料理人や流通業者が視察にくる。
養鱒業の未来は、この豊かな水の恵みを、食文化として発信できるか、或いは文化として語れる内容が伴っているかに懸っているようだ。

柿島養鱒の敷地にある猪之頭湧水
酒蔵の伝統を支える源泉
名水が必要不可欠である酒造業。猪之頭の南西、芝川町柚野地区にある富士錦酒造は創業300年超という県内屈指の老舗酒蔵だ。
18代目当主の清信一社長は神奈川県出身。妻朋子さんの実家である富士錦酒造に婿入りしたとき、井戸水を当たり前のように飲料にしていることに驚いた。一方、朋子さんは東京の大学に通っていた頃、水道水をそのまま飲もうとして注意されたことがあるという。「水を扱う事業者として、毎年2回欠かさず水質検査を行っていますが、まったく変化がない。富士山のろ過機能というのは凄いと日々実感します」と清社長。酒造家から見た富士山の湧水は「あたり(角)がない、やわらかで馴染みやすい」という。
近年、酒質の高さが評価されている静岡県の吟醸酒は、洗米から始まる仕込み工程で大量の水を使う。仕込み水を道具洗いにもふんだんに使えることに、県外出身の杜氏や蔵人が感心する。「原料米や職人は外から調達することもできるが、水だけは持って来られない。この地で酒造業を続けられるのは、この水があってこそ」と清社長は噛み締める。国際食品コンテストでも高く評価される『富士錦』には、「富士山湧水仕込」の文字が勲章のように輝いていた。

富士山湧水仕込をアピールした地酒
「世界文化遺産」と共生するために
富士常葉大学水環境デザイン室では、「いのちを育む水の旅」と称して定期的に富士山周辺の水量・水質を調査し、人の暮らしと水環境のかかわりについて研究している。
調査対象となった富士山南麓の富士市今泉湧水群・田宿川地区は、明治初期に富士の製糸業の発祥地となった湧水地帯。今も工場稼働期には深層の地下水が過剰に揚水され、水位が低下し、駿河湾の海水が入り込んで塩水化に傾いたり、湧水が枯渇するなど水環境にしばしば変化が見られる。
田宿川本流は1秒間に1トンもの流量があり、毎年7月にはたらい流し祭りも行われる。高度成長期にヘドロで汚染された苦い経験があり、地域住民が一丸となって浄化に努めた成果だ。その田宿川には絶滅危惧種の『ナガエミクリ』という貴重な水藻が群生している。これがしばしば異常発生して水位を上げる。富士山麓の茶畑で使用される化学肥料が原因で藻が育ち過ぎるからではないかとみられ、住民が川の清掃時にナガエミクリを伐採すると、水位はもとに戻る。
湧水や川の保全を考えるということは、その流域全体の暮らしと産業の在り方に向き合うこと。世界文化遺産と共生することになる富士山麓の人々にとって、避けて通れないテーマになりそうだ。(中日新聞富士山特集 2011年10月15日掲載より抜粋)
記事でもふれたように、酒造業は地域の水環境に大きく影響されます。水質によって酒の味が左右されるのは無論のこと、安定した仕込みのためには、水量や水温がつねに一定であることが必須条件だからです。
7月1日の中日新聞に掲載予定の富士山特集で、あらためて水資源について書こうと、先日、御殿場の根上酒造店を訪問しました。『金明』『富嶽泉』『富士自慢』というブランドで知られる蔵元で、社長の根上陽一さんが杜氏を兼務しています。

2013年1月1日。根上酒造店付近の富士山
古い記事ですが、1998年8月の毎日新聞『しずおか酒と人』で、根上さんのことをこんなふうに紹介しました。
蔵元自醸酒を応援しよう
先日、はせがわ酒店(東京都江東区)の新酒の会が開かれた新高輪プリンスホテルで、『十四代』(山形)の高木顕統さんにお会いしました。27歳で実家の高木酒造で酒造りを始め、初めて造った酒が通の間で評判になり、酒造界のイチローと異名をとるほどの人。パーティー会場でも彼の周囲にはつねに人垣ができ、オーラに照らされているようでした。
高木酒造では杜氏を置かず、高木さんがリーダーとなって地元の人と一緒に酒を造っています。杜氏や蔵人の減少により人材が確保できず、廃業してしまう蔵が多い中、高木さんのように蔵元自身が造る〈自醸酒〉が増えてきました。
酒造家の血を引くとはいえ、杜氏に比べたら素人同然の彼らが造る酒を、売り手も飲み手も最初は不安に思ったことでしょう。しかし酒質の点でプロの杜氏にひけをとらないということが、十四代の成果で見事に証明されました。
『金明』の根上酒造店(御殿場市)でも1990年から社長の根上陽一さんが酒を造っています。東京農大醸造科を卒業した根上さんは、家業を手伝うかたわら、蔵で働く越後杜氏のもとで酒造りを覚えました。杜氏が高齢を理由に引退を申し出たとき、意を決して自分で造ることに。「最初はちょろいもんだと思っていましたが、とんでもない。水質から何から教科書で学ぶ環境とは全く違い、失敗の連続。12月に搾りたてが間に合わず、お客様に迷惑をかけたこともありました」。
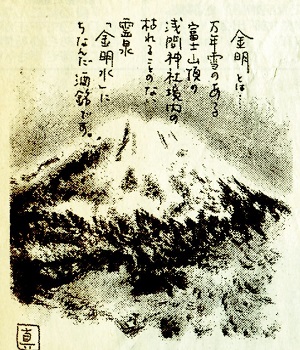
毎日新聞「しずおか酒と人」の挿絵
半自動化していた麹造りをすべて手作りに戻し、特定名称酒の比率も増やしたため、社長業との兼業は並大抵の忙しさではなく、4年後に病気で倒れてしまいます。やむをえず岩手の南部杜氏を手配したものの、やはり根上の伝統は自分で守ろうと奮起。現在は地元で3人、繁忙期にはさらに2人を雇い、経営と製造両面で奔走しています。
小売店への配達までは手が回らず、問屋主体にしていましたが、ヴィノスやまざき(静岡市)が吟醸酒を扱い、静岡の酒通に浸透し始めました。情報発信能力のある実力店のバックアップは、根上さんにさらなる奮起と酒質向上への課題を与えたようです。
「身を削る努力をするからには、混ざりけのない本当に純な酒、日本酒の伝統に立ち返った酒を造りたい」と根上さん。高木顕統さんのようなスターに・・・とは言いませんが、蔵元の姿勢をきちんと伝え、その意思が投影されるような酒を期待してやみません。(毎日新聞朝刊「しずおか酒と人」 1998年8月6日掲載)
自醸蔵となった根上酒造店の生産量は、根上さん一人で目の行き届く範囲の規模。必然的に仕込み期間が長くなり、「去年は夏のお盆前に1本仕込んで、ヘトヘトになった」と苦笑いします。
夏でも酒を仕込んでいると聞くと、大規模工場でオートメーション管理できる大手メーカーを想像しますが、根上さんのように、冬場に年間流通分を集中仕込みできず、長期で少量ずつ仕込む自醸蔵もあるのです。
夏場、仕込み蔵や貯蔵庫は冷蔵管理できるものの、蒸米を冷やしたり麹を造るとき、どうしても直接手で米にタッチする。この季節の最大の敵は、人間の手や指先に付着する雑菌なんですね。根上さんがヘトヘトになった理由は、自分の手や酒造道具の抗菌対策のせいだったそうです。
6月末は酒造年度が終わって各蔵元ともひと段落、という時期ですが、根上酒造店ではこれから大吟醸の仕込みに入るとのこと。いくら平地より2~3℃外気温が低いとはいえ、本来は冬の寒さの最も厳しい時期に仕込む特別仕様の酒にこれから挑むというのは、文字通り、身を削る作業ではないかと想像します。
気を抜けない手洗いや道具の手入れに欠かせないのがきれいな水。蔵の敷地にある自噴井戸からは、四六時中、富士山の雪解け水が噴出しています。「一時期、夏場にチョロチョロっとしか出なくなって焦りましたが、今はこのとおり」と根上さん。巨大な水亀ともいえる富士山の、年間を通して12~13℃という安定した水温と豊富な水量が、年間休みなく酒を造り続ける蔵の生命線なのだ・・・とあらためて実感しました。

自噴井戸をチェックする根上陽一社長
現在は全量、純米仕込みとし、自分でラベルデザインまで手掛ける根上さん。「軟水なんだけど、ちょっぴり発酵が進みやすい。この水に合った酒米を地元で育てるのがこれからの目標」。御殿場は県内屈指のコシヒカリ産地として知られていますが、山田錦や誉富士は、富士山の土との相性がイマイチだそう。酒造りを通して、富士山の土のこと、水のことが根上さんの中に得難い知識や経験として蓄積されていくんだと思います。
世界文化遺産のお膝元にこういう酒造家がいることをもっと知ってもらうべきだし、酒造界のスターになってもらいたい・・・今は、心からそう思います。

根上酒造店の地酒
『金明』醸造元 根上酒造店 http://www.at-s.com/gourmet/detail/3425.html
5月末にユネスコの諮問機関(イコモス)の評価が出てからは、「最初から自然遺産ではなく、文化遺産登録を目指せば、もっと登録は早かった」という関係者の声が印象に残っています。やっぱり文化の力って偉大なんですね。
2013年1月1日、家族で初詣した三保松原
文化遺産に登録されたとしても、富士山の場合、文化を育んだ自然を保護していくことも重要です。以前、富士山の水の恵みをテーマに、こんな記事を書きました。
湧水に育まれるニジマス養殖
『白糸の滝』の北、芝川の上流に広がる『猪之頭湧水群』はニジマス養殖で知られる。昭和11年に静岡県水産試験場富士養鱒場が設立したのを機に、猪之頭一帯で養殖池が作られ、一大養鱒地に。戦後は冷凍ニジマスが北米に輸出され、国内需要も右肩上がりに伸びた。
産業は成長・発展とともにリスクも伴う。台風や水害等の影響でしばしば変化する湧水量。加えて高度成長期には周辺に工場や事業所が進出し、水量は相対的に減少し始めた。リスクを避けた養鱒業者は市外・県外へ移転し、川魚消費の伸び悩みも手伝って、現在、猪之頭の養鱒業者は30軒足らずとなった。
柿島養鱒の岩本いづみ社長は、ニジマス本来の美味しさを見直してもらおうと、飼料添加物や人工色素に頼らない天然素材の餌を毎日作って与える。3児の母でもある岩本社長の考えは「色素を添加した、脂肪が不自然に多い魚は育てたくない」と明快。餌の自家製造は養鱒業では極めて珍しいという。
「魚が川の中で長い時間をかけ、自然に育つ環境を再現したい。それには豊富な流水量が不可欠」と案内してくれたのは、養殖池のすぐそばにある湧水ポイント。猪之頭はかつて「井之頭」と表記されていたそうだが、その名を象徴するような滝が水のカーテンのように岩肌を厚く覆い、川の各所で水がボコボコと湧き上がっている。今では国内外の名のある料理人や流通業者が視察にくる。
養鱒業の未来は、この豊かな水の恵みを、食文化として発信できるか、或いは文化として語れる内容が伴っているかに懸っているようだ。

柿島養鱒の敷地にある猪之頭湧水
酒蔵の伝統を支える源泉
名水が必要不可欠である酒造業。猪之頭の南西、芝川町柚野地区にある富士錦酒造は創業300年超という県内屈指の老舗酒蔵だ。
18代目当主の清信一社長は神奈川県出身。妻朋子さんの実家である富士錦酒造に婿入りしたとき、井戸水を当たり前のように飲料にしていることに驚いた。一方、朋子さんは東京の大学に通っていた頃、水道水をそのまま飲もうとして注意されたことがあるという。「水を扱う事業者として、毎年2回欠かさず水質検査を行っていますが、まったく変化がない。富士山のろ過機能というのは凄いと日々実感します」と清社長。酒造家から見た富士山の湧水は「あたり(角)がない、やわらかで馴染みやすい」という。
近年、酒質の高さが評価されている静岡県の吟醸酒は、洗米から始まる仕込み工程で大量の水を使う。仕込み水を道具洗いにもふんだんに使えることに、県外出身の杜氏や蔵人が感心する。「原料米や職人は外から調達することもできるが、水だけは持って来られない。この地で酒造業を続けられるのは、この水があってこそ」と清社長は噛み締める。国際食品コンテストでも高く評価される『富士錦』には、「富士山湧水仕込」の文字が勲章のように輝いていた。
富士山湧水仕込をアピールした地酒
「世界文化遺産」と共生するために
富士常葉大学水環境デザイン室では、「いのちを育む水の旅」と称して定期的に富士山周辺の水量・水質を調査し、人の暮らしと水環境のかかわりについて研究している。
調査対象となった富士山南麓の富士市今泉湧水群・田宿川地区は、明治初期に富士の製糸業の発祥地となった湧水地帯。今も工場稼働期には深層の地下水が過剰に揚水され、水位が低下し、駿河湾の海水が入り込んで塩水化に傾いたり、湧水が枯渇するなど水環境にしばしば変化が見られる。
田宿川本流は1秒間に1トンもの流量があり、毎年7月にはたらい流し祭りも行われる。高度成長期にヘドロで汚染された苦い経験があり、地域住民が一丸となって浄化に努めた成果だ。その田宿川には絶滅危惧種の『ナガエミクリ』という貴重な水藻が群生している。これがしばしば異常発生して水位を上げる。富士山麓の茶畑で使用される化学肥料が原因で藻が育ち過ぎるからではないかとみられ、住民が川の清掃時にナガエミクリを伐採すると、水位はもとに戻る。
湧水や川の保全を考えるということは、その流域全体の暮らしと産業の在り方に向き合うこと。世界文化遺産と共生することになる富士山麓の人々にとって、避けて通れないテーマになりそうだ。(中日新聞富士山特集 2011年10月15日掲載より抜粋)
記事でもふれたように、酒造業は地域の水環境に大きく影響されます。水質によって酒の味が左右されるのは無論のこと、安定した仕込みのためには、水量や水温がつねに一定であることが必須条件だからです。
7月1日の中日新聞に掲載予定の富士山特集で、あらためて水資源について書こうと、先日、御殿場の根上酒造店を訪問しました。『金明』『富嶽泉』『富士自慢』というブランドで知られる蔵元で、社長の根上陽一さんが杜氏を兼務しています。

2013年1月1日。根上酒造店付近の富士山
古い記事ですが、1998年8月の毎日新聞『しずおか酒と人』で、根上さんのことをこんなふうに紹介しました。
蔵元自醸酒を応援しよう
先日、はせがわ酒店(東京都江東区)の新酒の会が開かれた新高輪プリンスホテルで、『十四代』(山形)の高木顕統さんにお会いしました。27歳で実家の高木酒造で酒造りを始め、初めて造った酒が通の間で評判になり、酒造界のイチローと異名をとるほどの人。パーティー会場でも彼の周囲にはつねに人垣ができ、オーラに照らされているようでした。
高木酒造では杜氏を置かず、高木さんがリーダーとなって地元の人と一緒に酒を造っています。杜氏や蔵人の減少により人材が確保できず、廃業してしまう蔵が多い中、高木さんのように蔵元自身が造る〈自醸酒〉が増えてきました。
酒造家の血を引くとはいえ、杜氏に比べたら素人同然の彼らが造る酒を、売り手も飲み手も最初は不安に思ったことでしょう。しかし酒質の点でプロの杜氏にひけをとらないということが、十四代の成果で見事に証明されました。
『金明』の根上酒造店(御殿場市)でも1990年から社長の根上陽一さんが酒を造っています。東京農大醸造科を卒業した根上さんは、家業を手伝うかたわら、蔵で働く越後杜氏のもとで酒造りを覚えました。杜氏が高齢を理由に引退を申し出たとき、意を決して自分で造ることに。「最初はちょろいもんだと思っていましたが、とんでもない。水質から何から教科書で学ぶ環境とは全く違い、失敗の連続。12月に搾りたてが間に合わず、お客様に迷惑をかけたこともありました」。
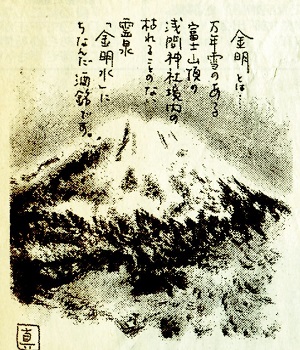
毎日新聞「しずおか酒と人」の挿絵
半自動化していた麹造りをすべて手作りに戻し、特定名称酒の比率も増やしたため、社長業との兼業は並大抵の忙しさではなく、4年後に病気で倒れてしまいます。やむをえず岩手の南部杜氏を手配したものの、やはり根上の伝統は自分で守ろうと奮起。現在は地元で3人、繁忙期にはさらに2人を雇い、経営と製造両面で奔走しています。
小売店への配達までは手が回らず、問屋主体にしていましたが、ヴィノスやまざき(静岡市)が吟醸酒を扱い、静岡の酒通に浸透し始めました。情報発信能力のある実力店のバックアップは、根上さんにさらなる奮起と酒質向上への課題を与えたようです。
「身を削る努力をするからには、混ざりけのない本当に純な酒、日本酒の伝統に立ち返った酒を造りたい」と根上さん。高木顕統さんのようなスターに・・・とは言いませんが、蔵元の姿勢をきちんと伝え、その意思が投影されるような酒を期待してやみません。(毎日新聞朝刊「しずおか酒と人」 1998年8月6日掲載)
自醸蔵となった根上酒造店の生産量は、根上さん一人で目の行き届く範囲の規模。必然的に仕込み期間が長くなり、「去年は夏のお盆前に1本仕込んで、ヘトヘトになった」と苦笑いします。
夏でも酒を仕込んでいると聞くと、大規模工場でオートメーション管理できる大手メーカーを想像しますが、根上さんのように、冬場に年間流通分を集中仕込みできず、長期で少量ずつ仕込む自醸蔵もあるのです。
夏場、仕込み蔵や貯蔵庫は冷蔵管理できるものの、蒸米を冷やしたり麹を造るとき、どうしても直接手で米にタッチする。この季節の最大の敵は、人間の手や指先に付着する雑菌なんですね。根上さんがヘトヘトになった理由は、自分の手や酒造道具の抗菌対策のせいだったそうです。
6月末は酒造年度が終わって各蔵元ともひと段落、という時期ですが、根上酒造店ではこれから大吟醸の仕込みに入るとのこと。いくら平地より2~3℃外気温が低いとはいえ、本来は冬の寒さの最も厳しい時期に仕込む特別仕様の酒にこれから挑むというのは、文字通り、身を削る作業ではないかと想像します。
気を抜けない手洗いや道具の手入れに欠かせないのがきれいな水。蔵の敷地にある自噴井戸からは、四六時中、富士山の雪解け水が噴出しています。「一時期、夏場にチョロチョロっとしか出なくなって焦りましたが、今はこのとおり」と根上さん。巨大な水亀ともいえる富士山の、年間を通して12~13℃という安定した水温と豊富な水量が、年間休みなく酒を造り続ける蔵の生命線なのだ・・・とあらためて実感しました。
自噴井戸をチェックする根上陽一社長
現在は全量、純米仕込みとし、自分でラベルデザインまで手掛ける根上さん。「軟水なんだけど、ちょっぴり発酵が進みやすい。この水に合った酒米を地元で育てるのがこれからの目標」。御殿場は県内屈指のコシヒカリ産地として知られていますが、山田錦や誉富士は、富士山の土との相性がイマイチだそう。酒造りを通して、富士山の土のこと、水のことが根上さんの中に得難い知識や経験として蓄積されていくんだと思います。
世界文化遺産のお膝元にこういう酒造家がいることをもっと知ってもらうべきだし、酒造界のスターになってもらいたい・・・今は、心からそう思います。
根上酒造店の地酒
『金明』醸造元 根上酒造店 http://www.at-s.com/gourmet/detail/3425.html
Posted by 日刊いーしず at 13:00


